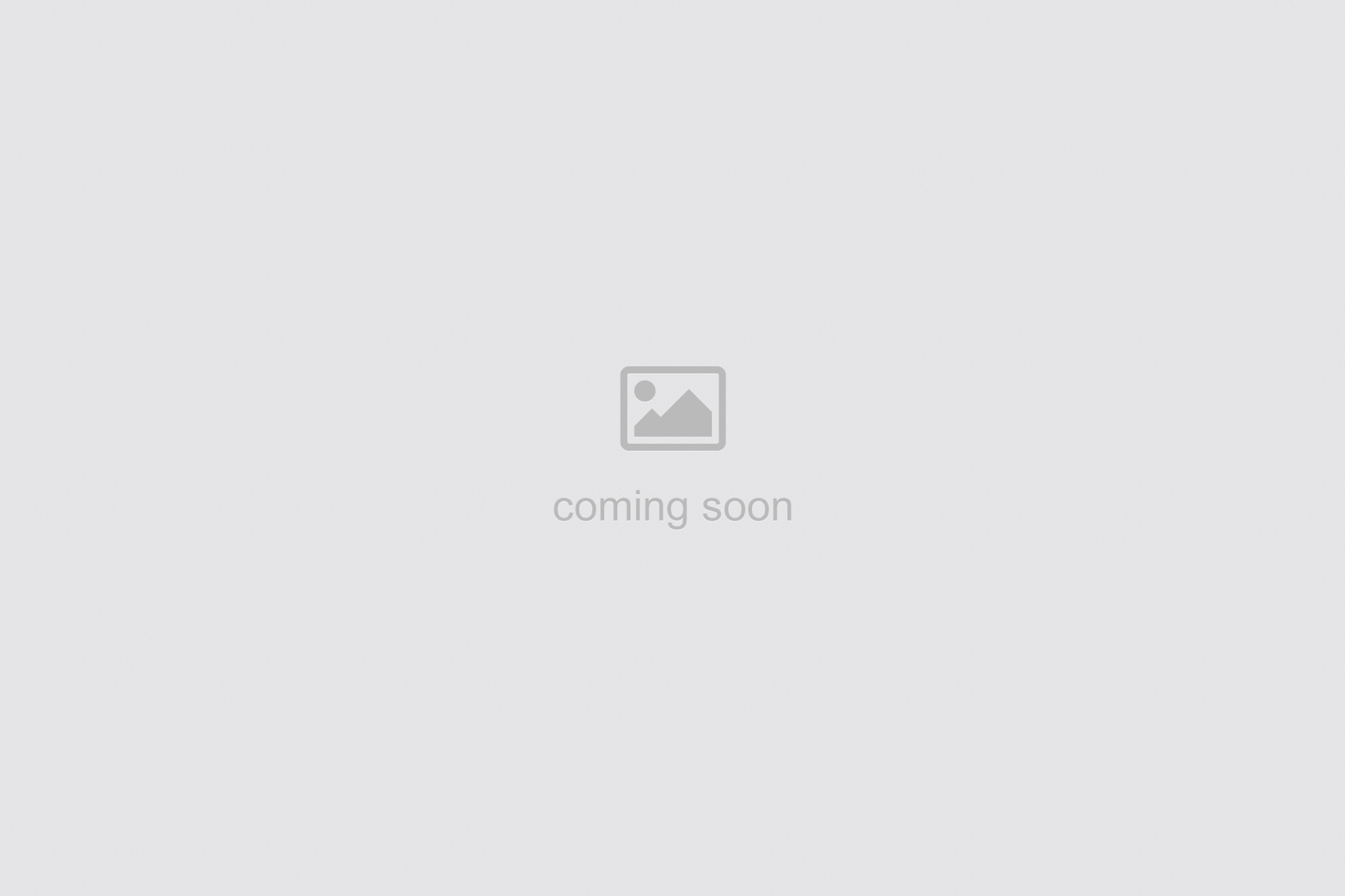よくあるご質問
よくあるご質問について
当園に寄せられるご質問の中から、特に問い合わせの多い項目について掲載致しております。下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。
Q&A(よくあるご質問と回答)
早苗幼稚園は昭和47年4月に開園した幼稚園ですが、平成28年4月には京都府内では第3番目となる『幼保連携型認定子ども園』に移行しました。
従来の幼稚園児(3~5歳児)は1号認定児として八幡市、枚方市、京田辺市在住のお子様を対象に幼稚園として受け付けを致します。
この幼稚園児の中で保護者の就労に伴い、お子様をお預かりする必要性のある園児は、2号認定児として各市役所窓口にお申し込み頂ければ、市窓口で受け付けが可能です。
0歳(6か月)~2歳児の乳幼児保育は、3号認定児として八幡市在住の保護者のみが対象となりますがお申し込みは八幡市保育幼稚園課にお問い合わせください。
その他、早苗幼稚園では在園児及び未就園児対象の一時預かり保育も実施しています。また、自園で調理する完全給食を月~土曜日実施しておりますので温かいお昼ご飯を提供しています。
1~3号認定に関するお問い合わせは随時承っていますので、お気軽に幼稚園までお尋ねください。
 075-981-2268
075-981-2268

新制度で従来の幼稚園型保育希望の場合1号認定児という名称で呼ばれ、完全給食以外は殆ど今まで同様の保育を提供します。詳細は幼稚園にいつでもお問合せください。(令和元年10月以降、3~5歳児の保育料は無償化になりました。 )
2号認定児については、保育園入園時に必要とされる要件等はかなり軽減されて、就労、就学、介護、疾病など全ての状況にも対応が可能です。
保育日数は年間300日、月~土曜日の、1日11時間を基本に、更に30分の延長保育も実施することになります。
就労時間数が月平均64時間(週2日8時間勤務)以上勤務される保護者の方なら、2号認定を受けることが可能です。
詳細については、お住いの市役所保育関係窓口でご確認ください。
3号認定児(未満児)については、現在八幡市在住保護者にのみ限定となりますが、生後6か月からの乳児さんをお預かりします。
保育時間、日数については2号認定児と同様です。
ご質問には随時対応しますので、幼稚園までお気軽にお尋ねください。
075-981-2268
早苗幼稚園では、一日の流れを設定保育という取り組みの中で子どもたちへの保育を行っています。
子どもの年齢と成長に合わせた保育を第一に考えた上で、各担任が日案、週案と呼ばれる保育計画に基き、各学期や季節を考えた取り組みで、行事や日常の活動など幼児期の体験が必要とされる内容を大切に、子どもたちと一緒に取り組んでいくように指導しています。
早苗幼稚園では、子どもが自由に伸び伸びと遊んで育つことを何よりも一番大切に考えており、そのためにも教職員全員が日々の保育に様々な工夫を採り入れ、早苗独自の教育理念の実践を心掛けるよう心を一つにして協力し合っています。
更に子どもの自立心や非認知能力を高める保育を第一義に考えて、何事に関しても子ども自身が自分の力で考え、最後までやり遂げることを大切に考えています。
また、仲間と協力し合い助け合いながら、試行錯誤を重ねて共同作業を進める中で、人との協調性、思い遣り考え、創造力を高める子どもに育てたいと願っています。
3年保育をお選びになる保護者が圧倒的に多く、2年保育で入園される方は私立園では少数派です。
幼少期は親の手元で子どもと直接関わりたいと考えるお母さんもおられる中、幼児教育の観点から言えば、子どもが満3歳になれば早目の入園を考えることをお勧めします。
少子化が加速する現状では周りに同年齢の子どもが少なく、親が一生懸命に関わることは素晴らしいことですが、子どもたちだけの世界を体験させることの意義は大きく、同年齢の子どもたちに囲まれて集団の中から学び合う必要性とチャンスを大切にして頂きたいので、年少組からの入園をお勧めします。
大人になり社会に巣立つ事を考えれば、小さい時から自然に社会性を習得出来るので、幼稚園での集団生活が子どもに与える影響はとても大きいです。
少人数制なら担任の目が全体に行き届くと考えて少人数を望まれる保護者が結構おられます。
それ自体は否定しませんが、幼稚園という空間はマンツーマン形式で勉学を教える場所ではありません。
幼稚園という環境に於いては、子どもたちが様々な「遊び」と「体験」を繰り返し積み重ねる一方で、保育者が子どもたちの内面的成長を援助し、最終目的は子どもの自立を支援するための場所なのです。
運動会のクラス対抗リレーや組体操、クラスで競い合う競技など、どれをとっても大勢で取り組むからこそ楽しさも倍増します。
劇遊びや音楽会での取り組みも、クラスの仲間と一緒に力を合わせてお芝居や合奏曲を作り上げるプロセスを通して達成感を味わい、たくさんの仲間と出会うところに喜びも楽しさも膨らむのです。
個性豊かなたくさんの仲間達に囲まれ、様々な遊びや行事を一緒に体験していくからこそ、子どもは更に大きく成長を遂げていくのです。
このようなグループ・ダイナミズムこそが、子どもをよりたくましく人間味豊かな人格形成へと導いていくので、少人数制では体験できない大きなメリットがあることを認識してください。
乳幼児期の子どもの育ちと理解力は大人とは大きく違うことを深く考えないで、大人の目線だけで考えた『早期教育』が優れていると勘違いし、良かれと考えて早期教育を子どもにさせている親がいます。
しかし、乳幼児期の子どもに必要なことを考えれば成長に欠かせない「遊び」が何よりも一番に楽しい活動であり、色々なことを学べる「遊び」という体験こそが、子どもにとっては如何に大切であるのかどうか気付いてあげてください。
6歳までの幼児期は、砂遊びや様々なごっこ遊び、おままごと遊びやお絵描き遊びなど、この時期にしか興味を示さない「遊び」があり、自分で見付けた「遊び」を幼児自らが工夫し、考えていくプロセスの中で自然に応用力や創造力が培われていきます。
その中から「1つ以上の方法や遊び方」を思い付く子どもに育ててあげることが、将来その子の可能性を更に広げることにつ繋がっていきます。
算数や読み書きのように絶対評価に基きたった1つの正解だけを求める学習には、子どもの「可能性」や「創造力」を伸ばす非認知能力は伸ばしてはくれません。
他方、子どもは「遊び」を通して他者との触れ合いや将来の人間関係を築く方法を自然に習得します。将来人として身に付ける必要のある協調性や会話力など、子ども自身が豊かな人格形成を目指していく上で必要とされるものと、早期教育がポイントを置く観点とは相反するものがあります。
「遊び」を通して自由で伸びやかに育まれる子どもは、他者との繋がりを自分自身で見つけ出す能力を伸ばし、協調性や社交性を伸ばすチャンスに恵まれる結果、子どもの将来を考えた幼児教育の取り組みが不可欠であることを真剣に考えてください。
乳幼児期から早期に取り組んでも支障ないものとしては、音楽、スポーツ、絵画、習字など子どもが五感を使って習得する練習事については、早い段階から始める効果が十分に期待出来るでしょう。これらに共通することは、子どもが自らの感性や個性を伸ばせる可能性があることと、そこには相対的な評価でしか判断出来ない「何通りもの考え方や受止め方」が可能になり、創造力や感性の世界観に重点が置かれることです。
幼児期の早期教育の特徴としては反復学習や繰り返し学習に重点を置く勉強方法が多く、単に「一つだけの答え」を求めさせる作業になる為、子どもの創造力や情操教育を高めていくものとは大きく掛け離れてしまいます。それらは「正解」を求める為に絶対評価に基づいた100点に近付く為の学習が重視されるに過ぎません。
更に乳幼児期に於ける早期教育の弊害としては、子どもの脳の発達を無視した取り組みです。
ある面では多少の成果を見せたとしても、豊かな「遊び」を通して習得した発想力や創造力に加え、情操教育を体験している子どもたちは、やがて学習が始まれば同様の発想力を発揮するので、結果的には早期教育を受けた子どもたちに後年追い付きます。
追い付かれやがて追い越された時の前者の子どもたちは、思春期に入ると幼児期に遊び体験をさせて貰えなかった反動と恨みの矛先を自身の親に向けるようになるのです。
小学校高学年くらいまでは早期教育の成果は期待出来ますが、「遊び」を体得した子どもの感性や創造力はそれ以降徐々に発揮される結果、後から追い付かれ追い越されるプレッシャーに圧され、やる気や気力を失うなど、思春期を境に登校拒否や人間(親)不信に陥るなど、取り返しのつかない芽を植え付ける危険性を想像してみてください。
5歳児の奏でる音楽や3歳児の描いた絵画は単に相対的な評価対象が可能で、子ども自身も五感を使う「遊び心」を満たす余地がある中で、練習を重ねて次第に自信を深めていきます。
つまり子どもの感性や創造力は伸ばせば伸ばすほど豊かになり、五感を使う練習そのものが将来の可能性を更に伸ばすことに繋がるのです。
小学生になれば絶対評価に基づく「勉強」を避けて通れないのだから、せめて6歳までの乳幼児期に於いては豊かな「遊び」を通して人とのつながりや、子どもの個性を大きく育ててることに重点を置くべきだと思います。
子どもたちは十人十色!
満三歳になったばかりの年少組さんたちは、「月齢」といって3ケ月程度を一つの区切りに4つのグループ分けが出来ます。
3歳児の発達段階を4つに分けて考えれば、ご自身のお子さんと他の誰かを比較したところで、そもそも個性の違う一人ひとりを比較対象にすること自体も正しくはありません。
入園当初は泣いている子どもも、5月の連休が終わるころにはお友だちと一緒に遊ぶ楽しさを覚え、次第に協調して遊ぶことにも慣れてきます。
子どもたちはそれぞれが、将来への「自立」を目指しながら集団の中で揉まれて鍛えられます。
園生活に溶け込むスピードは千差万別。
温かく大きなお気持ちでお子さんの成長を見守ってあげてください。
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
075-981-2268